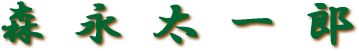 |
||
| 困難に負けず自分の夢を貫き通した製菓王 | ||
| 伊万里神社 |  |
エンゼルマーク |
| 森永太一郎 (1865〜1957) |
||
| 「これだ。」太一郎はベンチからはね起き、小さな紙切れをつまみ上げました。 アメリカ、サンフランシスコの公園でのことです。太一郎が拾い上げたのは、子供たちが捨てたキャラメルの包み紙でした。「日本の子供たちも、きっと喜ぶにちがいない。」電撃のようなひらめきが太一郎を奮い立たせました。一片の包み紙が「製菓王」森永太一郎を誕生させるきっかけとなったのです。 太一郎は1865年(慶応元年)六月一日、父常次郎、母キクの長男として伊万里で生まれました。森永家は焼き物や魚類を商う卸問屋で祖父太兵衛の代までは伊万里でも有数の商家でしたが、家運が傾き、父が若くして亡くなったため、財産もすっかり人手に渡ってしまいました。母キクはわずか六つの太一郎を連れて、伊万里の町から約三・五キロほど北の岩建立にある実家へ帰りました。 母キクの生家である力武家も、もとは裕福な農家でしたが、人に貸した金が取れなくなったのが原因で没落していました。その上、母が再婚することになり、太一郎はひとりぼっちになってしまいました。 そんな太一郎に、深い愛情をそそいでくれたのは祖母のチカでした。あるとき太一郎は、拾った金を隠し持っていたのをこの祖母に見つかり、自分で働いて金もうけをすることの大切さをこんこんと諭されました。この教えは、生涯太一郎の心に生き続けたと言われています。 その後太一郎はチカのもとばかりにいるわけもいかず、伯父や伯母の家を転々としました。そのころ、川久保雄平という人が、本屋のかたわら塾を開いていましたので、太一郎は伯父たちの世話で店員として住みこみ、夜勉強を習いました。そのと十二歳でしたが、太一郎の熱心さは目を見張るばかりで、わずか一年ほどの間に学問はめきめき上達し、先生に代わって講義をするほどになったということです。 やがて太一郎は、伯父山崎文左衛門に引き取られました。 「これで、お前がすきなように商売をしろ。」 文左右衛門はそういって、天秤棒とざるに桶、それに五十銭を太一郎にくれました。文左衛門は行商人から焼き物問屋の大商人に成功したほどの人でしたから、太一郎にも自力で商売を覚えさせようとしたのでしょう。数日すると、天秤棒をかつぎ、大声でコンニャクを売り歩く少年の姿が見られるようになりました。ある日、コンニャク屋の主人が、「品は落ちるが、見かけは変わらない。安く卸してやるからこれを売ってみろ。もっともうかるぞ。」と太一郎にすすめました。太一郎は「もうけは多くても、悪い品物は売りたくありません。」といってきっぱりと断りました。「粗悪な品を商ってはならぬ。」という伯父文左右衛門の教えを、太一郎は子供のころから身につけたのでした。 太一郎が本格的に商売の勉強を始めたのは、1879年(明治十二年)、十二歳の暮れのことでした。伊万里一の大店「堀七」に奉公し、ここで主人の太兵衛から商売人になるための多くのことを学びました。 しかし、太一郎は、もっと広い舞台で経験を積みたいという希望をおさえきれず、横浜に出て、陶器の貿易商、有田屋に勤めることになりました。田舎者の太一郎はまだ十七歳でしたが、持ち前の根性と才覚ですばらしい業績を上げました。東京の大問屋を相手に伊万里焼を売りさばき、当時の金で毎月二万円もの驚くべき商いをやってのけました。主人から大事にされた太一郎が、その世話で鎌倉の小坂セキと結婚したのは1884年(明治十七年)、二十一歳の時でした。 ところが、その幸運も長くは続かず、有田屋は破産してしまいました文無しになった太一郎は九谷焼の貿易商の店員となり、焼き物を売り込むためアメリカに行くことにしました。太一郎が二十四歳のときでした。長女が生まれていましたが、妻のセキは快く渡米を見送りました。 けれども、アメリカでの商売は思うようにはいかず、さすがの太一郎もやけになり、酒をあおると公園のベンチに寝ころがりました。そのときだったのです。キャラメルの包み紙がかれの目にとびこんできたのは。 さっそく太一郎は菓子工場を探してかけずり回りました。しかし、日本人をやとってくれるところはどこにもありません。生きていくためには、しかたなく農園やホテル、邸宅などを転々として力仕事をするよりほかありませんでした。その間に熱心なキリスト教信者になっていた太一郎は、願いが神に通じたのか、ついにキャンディー工場に働くことができるようになりました。 パンやケーキの作り方を身につけたい一心から、昼も夜も働き続けました。白人の職人からはひどい差別を受けましたが、ますます闘志を燃やしてがんばりました。 洋菓子の製法を身につけた太一郎が日本へ帰ってきたのは、1899年(明治三十二年)の六月です。すでに三十五歳でした。その年の八月、東京赤坂に念願の「森永西洋菓子製造所」が誕生しました。わずか二坪のちっぽけな工場でしたが、太一郎はマシュマロ作りに熱中しました。日本での太一郎の菓子製造がついにスタートしたのです。 ところが、お菓子は上出来なのに、なじみのない西洋菓子を売ってくれる店は一軒も見つかりませんでした。太一郎は、外から見えるようにガラス戸で囲んだ箱車を思いつき、お菓子を積んで売り歩くことにしました。やがて車のあとから、ぞろぞろと子供たちがついてくるようになりました。 天使の子供が翼を広げた森永のエンゼル・マークは、「子供に喜びを」という太一郎の願いから生まれたものです。森永のお菓子は、エンジェルの翼に乗って売れに売れ、太一郎は「製菓王」とたたえられるようになりました。かれの夢はみごとに花開いのでした。 太一郎は1937年(昭和十二年)一月、波乱の人生を閉じました。七十三歳でした。かれの銅像は伊万里神社の境内にあって伊万里の子供たちをやさしく見守っています。 |
||